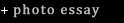本国に打電した。大場さんの写真が撮れました!と。編集は頑張ったね、と、初めてほめてくれた。自分でもねばった甲斐があった。仕事とはかように運ばなくてはならないものだと生まれて初めて知った。これが本物のプロフェッショナルな仕事なのだと。
私の次の仕事は、このフィルムを編集部に持ち帰ることである。で、ここでアドバイスを受けた。わかっているのだろうな?カメラはどうでもいいけれど、フィルムは肌身離さず持ち帰るのだぞ!と。もちろんです!と。ここ北極で撮影したフィルムは、ボストンバッグいっぱいになっていた。そのバッグにはフィルムだけ入れて、すべてX線は通さなかった。
空港までみんなが送ってくれた。別れはやはり辛いもの。ホテルにバイトに来ていた女の子が、私をギュッと抱きしめた。私は、ぽかんとしてしまった。再び小さなジェット機に乗り込む。万感の思いを込めて、ジェット機はエンジンを吹かす。ふわり宙に浮くとそのまま南へ飛び立った。
イエローナイフ上空はすでに雪はなかった。夕日を西に、東にブロッケンを抱えて。エドモントンに着いても、落ち着かなかった。初めてのエドモントンでは、食事は何をたのんでよいのかわからず、巨大なハンバーガーを深夜に食べてしまったが、今回もチンプンカンプンなオーダー。巨大なサラダを頼んでしまった。とにかく抱えているフィルムが落ち着かないのだ。


あとは何処でどう乗り換えたのか、まるで覚えていない。ただ、機が太陽を追いかけるように飛んでいたのはわかる。地球をどちらに向かって飛んでいるのかがよくわかるのだ。
久々に生国の地を踏んだ。成田には編集部から御迎えのハイヤーが来ていた。現像所に直行し、そのまま入稿するからだ。うれしかったのは、嫁さんが迎えに来ていてくれたことだ。みんなで会社までは帰ったが、嫁はそのまま大荷物とともに自宅に帰してしまった。

申し訳ない。せっかく迎えに来てくれていたのに。ただ謝るしかなかった。ほんとに新婚だったのに。
編集部に入るのには、少し緊張した。エレベーターを降り、編集部に入り込む前に挨拶した。鈴木高宇、ただいま帰りました。みなさんにはご迷惑をおかけしましたが無事に撮影ができました!と。編集部の隅から隅まで拍手が沸き起こった。うれしかった。
大場さんを北極で捉えた写真はすぐに仕上がった。現地で現像してどうのこうのより、1日半で帰国できるのだから、それで現像して入稿してしまえとなったのだ。まず、新聞社や通信会社に写真が配信された。そして、私の記憶がただしければ、その日は週刊誌の入稿日でもあったので、私は最後まで付き合うことになった。
当日の夕刊、翌日の朝刊を飾ったのは今でも記憶にある。かなりブレテいるが、機内から北極海にテントとたたずむ大場さんの姿と、日の丸を持ってスキーを履いた大場さんの写真だった。全国の新聞を何枚もの写真が飾ったのは後にも先にもこれっきりだ。まさにカメラマン冥利といえよう。


ところで、大場さんの北極点でのフィルムは?預かってこなかった???はい。全員忘れていました。大場さんから預かった日記とフィルムの中に北極点でのフィルムは含まれていなかった。もう、大笑いするしかなかった。まあ、大場さんの御蔭で私の写真が一面を飾れたのだが。まあ、みんな許してくれるだろう。ここだけの話だから。
当時、北極点付近での3回目の補給では、本当にみんなが安心してくつろいでしまった感がある。正直、みんながリラックスしていたと思う。それは、やはり地球の天辺で、大場さんに会えた喜びが勝っていたからだといえよう。
そう、この話は今だから書ける、ここだけの話なのである。

それからの私は、ずーっと、ポッカーンとしていた。何も手に着かないとはこのことだ。毎日毎日暗室作業や、撮影助手をしていた忙しい日々が嘘のようだった。フリーになりました、といってすぐに仕事はないのだった。幸い先輩や知人に助けられ営業なども少しはしていた。
少しずつ記者会見の仕事などいただきながら、私はカメラマンとして自立していった。気がつけば忙しい日々になっていた。その間も大場さんは春の北極海を横断していた。やはり、私の懸念していた通り、リードが問題だったようだ。それでも、大場さんは見事横断しきった。見事だった。
ワードハント島への取材には通信会社の方が行かれたようだ。なぜだろう、その写真には、あの北極点の片隅での出来事のような感動はなかった。
大場さんの凱旋帰国に成田へ取材に行った。どこからこれだけの報道陣が集まってきたのだろうか、帰国ロビーはたちまち大変な人だかりになった。マスコミにもみくちゃにされ、会見を行った。
この辺のことは当時の新聞やテレビのニュースを覚えている方もいらっしゃるだろう。大場さんは、最早、私の手から遠ざかった偉人になっていた。しばらくは大場さん関連の取材も続いた。これから先の大場さんは、もう皆さんの方がよくご存じだろう。

翌年、大場さんは南極大陸単独徒歩横断をいとも簡単に成し遂げてしまった。大スポンサーも付いた。装備に不足はない。
東京でクルマを走らせていると、ラジオから大場さんの南極中継が入る。衛星携帯電話を太陽電池で電源を補給。隣近所から電話している感覚で、北極でのような緊張感は、まったく感じられない。
一体、あの4度目の挑戦の悪戦苦闘の北極海は何だったのだろう。それだけ北極海の自然が厳しかったということだろうか。南極は夏季冒険することが可能であるが、北極海は厳冬期でなくては不可能なことも起因しているだろう。
ここから先の大場さんのことは実は良く知らない。どんどん先に進んでいるようだ。現在は山形に冒険学校を開校し、活躍されている。子供たちに伝えたい、これは昔からの悲願だったようだ。
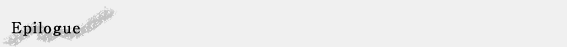

この北極点遠征記は、ひよこカメラマンの見地から書き記したもので、偏見が多々あるかもしれない。この年になって成熟した大人の発言とも言えないだろうが、当時間違いなく自分が感じた心情を記憶だけをもとに書き記したものである。それは大人でない発言でもあるし、子供じみているかもしれない。しかし当時確かに感じた違和感は、この遠征記を一気に書き記すことができるほど未だ焼き付いていたのだ。
実際の大場さんの遠征記とは若干順序が前後していることがあるのでご了承願いたい。大場さんの冒険記やエッセイは数多く発刊されているので、それらを読んでみると、正確な事象が書き記されているので、本当のところがわかるかもしれない。ただこのような、まず人目に触れることはないであろう黒子のカメラマンの姿が、このような形で書き記されることとなるとは自分でも思わなかったし、墓場まで背負っていくつもりであった。カメラマンは何処までいっても裏方の仕事師なのだ。
新米のひよこカメラマンに、どこまで世界的常識やアドリブができたのか、通用したのか、それは誰の目に見ても当時の私に果たせなかった事実である。ただ、人間、ひとつずつ経験を積み重ねて人生を豊かにしていく生き物である。それがいきなり極地での人の生死を左右する現場に飛び込んでしまったから大変だった。あのような時、人間の本性が出るから、それは恐ろしい。当然私の実力も出てしまったのである。素晴らしい写真は撮れるかもしれないが、人の心や感情までは捉えられなかったのかもしれない。そのことを踏まえ、今後の人生に生かせていけたら幸いだ。

北極は素晴らしい場所だった。今になって思えば人間関係も面白かった。ただ、そう言えるようになったのは、つい最近のことである。13年、私の中で北極は消化できない存在だった。それは大自然云々ではなく、やはり人間関係に起因しているのだ。
今度、極地に赴くなら、私はどんなピクチャーストーリーが描けるだろうか。極地は人間をよせつけない厳しい世界だ。そこに人間性のあるストーリーがあるなら、私はまた旅発つのだろうか。北極病は私の中で未だに燻っている。
ただ、ただひとつ私に言えることは、人間やる気になれば、物事は必ず達成できる、報われる、ということである。それは例え人生の大切な何かと差し違えてでも。
たった一枚の写真を撮るために、自分の中では失ったものもあった。それは誰のせいとか、誰かが悪いとか、そういうことではなく、究極、人間性の極限性が試される世界だったような気がするからだ。

最後に、北極行きを許可してくださった、たくさんの方々、応援して下った方々、様々な出会いを作ってくださった大場さんに、感謝とともにお礼を述べたい。
2010.08.27
写真家 鈴木高宇 東京にて
TAKANE SUZUKI In Tokyo Japan