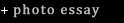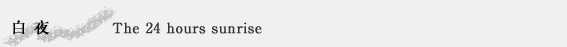

北側の窓からは深夜になっても夕日とも朝日とも判別の付かない幻想的な陽が射してくる。どうやら太陽は完全に沈まなくなったようだった。昼間は普通に明るいが、太陽の南中高度はかなり低い。深夜このような光になる白夜の一番美しい時間帯だ。なんせ、日本だったら数分で終わってしまう朝日や夕日の、細いライティングが何時間も続くのだ。カメラマンにとって、シャッターチャンスが延々続く不思議な世界だった。しかも昼間は蜃気楼が見え始めたのだ。
私は思い切って、レゾリュートの丘に登った。レゾリュートの丘、とは、私が勝手に命名したものだ。レゾリュートの丘の上からは絶景だった。地平線の果てに沈まぬ太陽が動いて行くのだ。私はこれを連続写真にしたかった。Nikon F3 にAi AF NIKKOR20-35mmF2.8Dを装着。カメラは剥き出しのまま、なんの保温対策もとらなかった。カメラはまったく平気だった。風が強かったので、三脚に岩を縛り付け紐で吊るし、安定感を高めた。
しかし、カメラは平気でも人間は大変だ。私はせめて風除けの壁が欲しかった。遮るものがなにもないからだ。いったんガレージへ行き、鋸を借りた。雪はスコップでは堅過ぎて、鋸で切り出さないと切り出せなかった。汗をかきながらせっせと切り出してゆく。なんとか壁はできた。風をシャットアウトするだけでかなり暖かい。私はザックから本を取り出し、極寒のなか読書を始めた。シャッターを切るのは1時間ごとで、合計6時間。たった6時間耐えればよいのだ。
ブリザードの中の読書というのも、なかなかおつなもので、けっこう楽しい。

指先はかなり凍えたが凍傷にだけは気をつけていた。ここではちょっと油断すると軽い凍傷にはすぐなってしまう。露出させてしまった耳などは火傷のように水ぶくれになるのだ。
一時間ごと、考えたデータでシャッターを切っていく。最後の最後、太陽は雲に隠れてしまった。それでも、わずかな光の時にシャッターを切らせてもらえた。珍しく感激した。そのあと、不意を突いたように太陽が明るく輝いた。あー、もうちょっとの判断が甘かった。それはまるで今回の遠征を示唆しているようではないか。

私はみんなが、イヌイット居留地遺跡見物とか、さそってもらえなかったので、自分で探して歩いた。テリーさんにも聞いて、なんとなく場所を探しだしたのだ。息抜きのこれですら無視されているのだから大変だ。まあ、拗ねている場合ではない。取材できるものはすべて撮る。そこはクジラの骨が屋根の梁の跡となって残っていた。残照が美しく骨を照らしていた。振り返ると大きな氷山も照らしだされていた。槍の先のような結晶も雪原に広がっていた。過去、私の山行はすべて単独行だった。なんだかたった一人の北極にいるようで楽しかった。
どうやら、今回の騒動と私の単独行はなにか因縁めいているような気がしなくもない。協調性に欠けるのではなく、どうしても馴染めなかった。

この日は朝からみんなが外でわいわいやっている。どうも暖かくなってきたので春のピクニックなのだそうだ。外にはスノーモービルが何台も用意され、後部には引かれる橇が繋がれている。
これは貴重な体験だ。なんとイヌイットの人たちのピクニックだからだ。普段、彼らはほとんど家に閉じこもっている。なんせ、寒さが寒さなので致し方ない。よって、このエリアでは酒は禁止されている。酔って騒いで喧嘩して、屋外で凍死というのが多かったからだそうだ。よって私はやけ酒やりたくても、まったくできなかった。外国人が持ち込む分にはいいのだが、地元にはまったくないのだ。いや、あるにはあった。0.1%のビアーが。私はそれでもアルコールが抜けきっていたので、気分だけは味わうことができたのだった。


さて、スノーモービルはエンジンが吠え、風を切り、海岸線を走る。私は後ろの橇に乗せてもらった。橇といってもベニヤ板で覆われた箱型の橇。いわばボックスの中に入っていただけなのだが、猛烈に足先が痛い。風を切って走るのがこんなに痛いだなんて思わなかった。1時間も走っただろうか。凍りついた海を走り、丘に登り、すごく走った。到着したのが、よくわからないのだが、湖の上だという。各々イグルーを作る人、テントを張る人、ストーブを焚く人、それぞれ役割を果たしていた。そして、ドリルで氷に穴をあけ、魚釣りを始める。釣り竿はない。18cmくらいの木の棒に糸を巻きつけてあるのを穴に落としていくだけだ。すると、ほんとに釣れるのだ。魚が。ここで魚が釣れなかったら、とても湖の上とは思えない。
北極は不思議な環境だ。生命の気配すら感じられない極寒の中、確かに生命が蠢いている。空から見下ろせば、ジャコウウシが小さく点在したりする。北極狐だって生きているのだ。ホッキョクグマには会えなかったが、この氷原のどこかに息づいているに違いない。そう考えるとなにか神秘的な感慨にふけるのである。

さて、その湖の氷だって恐ろしく分厚い。1mはあるだろうか、本当に分厚い。魚は釣りあげられる、少しぴくぴくして、たちまち凍てついてしまう。それに粉末醤油をかけて食べる。まるでルイベのようだ。醤油も粉末でないと凍りついてしまう。醤油はここレゾリュートでも大人気だ。
帰り途は陸地を進んだ。見たこともないハーフパイプのような道を行く。どうやら夏場は川らしい。今日は久々に有意義な一日だった。なにか吹っ切れたように、爽やかな極寒の風が吹いていた。

大場さんは北極点に到達した。それは他に単独徒歩で北極点を目指していた日本人冒険家と一日違いだった。
大場さんからは再び、補給要請が入った。これが自分にとって最後のチャンスだった。ここでもテリーさんの御世話になった、鈴木さんも行くのでしょ!Yes! me too ! この一言がなかなか言えなかった自分がいた。でも言えた。もどかしくて仕方がない。

再びツインオッターはプロペラ全開。が、今回は数日北緯80度、ユーレイカの気象観測所で待機となる。北極点付近でのアイスフォグが酷いらしい。飛んでも氷の状態が見えなければ着氷することはできない。しかもこの辺りでも雪が少なくなっているし、雪解けも進んでいるように感じた。季節は確実に春なのである。
この観測所には娯楽施設があり、ビリヤードなどしながら時間を潰すしかなかった。酒でもあればいうことなかったのだが、事態はそんな気分ではなかった。
またもやピリピリモードである。困ったものだが、自然相手ではどうにもならない。時間だけがただ虚しく過ぎてゆく。
そしてある日、Maybeその一言で始まった。たぶん大丈夫だろうとの機長の判断だ。Maybeとは多分の中では可能性が一番低い言葉だ。現在ならここで汗をかいた絵文字が出てきそうだ。それでも、我々は出発した。相変わらずガソリン臭い機内だ。もちろん禁煙。考え方によっては爆弾と一緒に飛んでいるようなものだからだ。
北極海に出て驚いた。このリードの広がり方は一体何なのだ。途方もなく氷の割れ目は広がり、今回補給できたとして、一体どうやってこの氷の海を渡るのか。かなり心配になったものの私にはどうすることもできない。大場さんの現在位置をたどると、かなり流されてはいるが、しっかりと目的地のワードハント島へ向かっていた。

ツインオッターは北極点の手前で旋回し始める。遂に大場さんの居る場所だ。雲はあったが、アイスフォグはなく天候は上々。今回はシーバーが通じない。だが今回は大場さん宛てに手紙が託されていた。まず肝心なのが氷の滑走路である。まっ平らな長さ300m以上の氷の滑走路が必要であること。これがないと着氷できない。
大場さんの姿が見えた。今度は近くから見ることができた。機長は着氷体制に入る。例によって、失速寸前まで速度が落とされる。気持ち悪いくらい機が揺れる。かなりの至近距離で大場さんが見えた。私は機内から全身全霊を込めてシャッターを切った。それは一瞬の出来事だった。大場さんはテントの脇で両手を振っていた。
しかし、その滑走路には降りられないのか、機は何度も旋回を繰り返す。まだかよ?というくらい機長は慎重に氷の状態を確かめる。それからどれくらい時間がたったのだろう。ようやく安心したのか、滑走路を決め着氷した。いつもながらプロペラの逆回転は凄い。そしてツインオッターは何事もなかったかのように安定して着氷したのだった。しかし、北極点でのパイロットは一発判断だった。聞けば、あのパイロットは北極一の凄腕なのだそうだ。でも、今回のパイロットも腕が悪いわけではない。これが熟練していても普通なのだ。


降りてみると、そこには大場さんの姿がなかった。はて?どこに降りたのだろう。あの白い氷原を何度も旋回されると現在位置がまったく判別できなくなるのに機長はちゃんとわかっているのだから凄い。
大場さーん!スタッフが叫ぶ。しばらくしてプレシャーリッジの陰からスキーを履いた大場さんが、ひょっこりと姿を現した。こちらが必死に叫んでいるのに大場さんはひょいと遠くを眺めていた。再会の瞬間だった。
私は比較的冷静にシャッターを切っていった。当時オートフォーカスもあったが、私はマニュアルフォーカスだった。ピントリングは寒さでおかしくなることなくスムーズに動いた。カシュン、カシュン、と軽快にシャッターも切れる。ボディはNikon F4 、望遠ズームは初代Ai AF NIKKOR 80-200mmF2.8sだ。気温も比較的暖かく20度。もちろんマイナスである。ENGのカメラマンも一緒にカメラを回す。私は雪をかぶった落とし穴に落ちないよう、カメラを大場さんにむけながらバックで一緒に歩く。待ちに待ったシャッターチャンスはあっけないくらい軽快に進む。雪景色の露出にも私は強かった。ポジフィルム1/3EV刻みで適性露出が一発で出せる自信があった。すべてが余裕だった。
大場さんは、あれ?鈴木君も来ていたの?くらいの軽い勢い。そうだろう、まさかここに控えていたとは想像もつかないだろう。こうして再会できて良かった。本当によかった。

滞在時間はそんなに長くいられないはずだったのに1時間以上ゆっくりできた。氷点下40度とか50度だと、5分、10分ですばやく補給を行わなくてはなないのだが、20度だと、比較的余裕である。機長もエンジンカバーは片方しかかけなかった。打ち合わせをスタッフとすばやく行い、時計をカナダ時間に合わせ直すなどすると、記念写真を撮る余裕さえあった。そしてみんな笑顔が絶えなかった。
もう、大場さんの顔にみなぎる活力が強く感じられた。この大場さんの顔を見ていると本当に横断達成が可能なような気がしてくるから不思議だ。空からみた北極海はまだまだ魔物だ。簡単に走破できるような氷原ではないのに。
別れの時が来た。すべての引き継ぎができた。もう、救難発信機を補給要請代わりに使わなくていいようにちゃんとした送信機を渡すこともできた。北極点を過ぎて、大場さんの装備は完璧なものとなった。別れ際、帰りの飛行機で食べる予定のカップラーメンが何故か雪原に出されていたのだが、それも大場さんに取られてしまった。し、しかたない。こうゆうものにも飢えているはず。ま、これは我々の間では笑い話になってしまったが。

エンジンカバーが外される。プロペラは回りだした。機内に入るとみんな大場さんのいる方に座る。大場さんはいつまでも手を振っていた。我々も手を振り続ける。ツインオッターが飛び立つ、この最後までシャッターは切られ続けた。
一世一代の大仕事は終了した。特にスタッフの解放感は得も言われぬものがあっただろう。大場さんの命を背負っているのだから。そして、これからも。