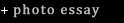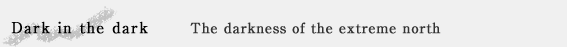
最初の緊急フライトの話が来たのは、レゾリュート入りしてからだいぶたったある日のことだった。飛行機はファーストエアーという極北の専門航空会社。天然の氷の滑走路で発着できる世界でも稀なエキスパートなのである。しかも氷は流氷だ。北極海に大陸はない。すべて凍りついているのだが、海流はかなり強い。

ここで少し北極海について説明すると、北極の氷は絶えず動いていて、氷と氷どうしがぶつかりあい、プレッシャーリッジという氷の乱氷帯ができる。反対に氷どうしの隙間はリードと呼ばれ、北極海がすっぽり穴をあけている。これに落ちると大変なのだ。プレッシャーリッジを乗り越え、リードが開いていたら、どっちに行こうかな?と、紆余曲折、スキーを履いて、大荷物の橇を引いてひたすら歩くのだ。そこへ極寒の寒気。体力の消耗は並みのものではない。大場さんは北極点にあと一歩のところまできているのに、一日で100km近くも流されてしまったのだ。
結局、今回のフライトの話はなくなってしまった。しかし、今回、出発に際して問題が起きた。私の機材が多すぎるというのだ。確かにカメラザックは大きいが、中身は少ない。軽量化したボディ3台。レンズ3本、コンパクトカメラ1台、と、こんな希少な現場としては厳密に厳選し、軽量化を図ったつもりだったが、これがスタッフの怒りを買った。
機材を軽量化するのには理由がある。氷の短い滑走路で発進するとき、機が重いと離氷できないのだ。それにエンジントラブルがあったとき、もしも片方のエンジンしか使えなくなった場合、機が軽くないと陸地まで持たない、などの問題だ。実際、過去にはエンジントラブルがあり、テープとフィルム以外、すべて機内から海中に投棄した事例がある。
飛行機は双発プロペラ機、ツインオッター。機内はガ

ソリンのドラム缶が御客様。我々取材班はゴミみたいなものなのだ。なぜガソリンのドラム缶が御客様であるのかは、後に述べるとしよう。
それにしても、酷い怒りようだった。これを機に、ますます険悪な仲になる。それでも、すべてを投げ出して逃げたくなる気持ちにはならなかった。今現在、ここまで来たら、北極点で大場さんをスチールフォトできちんと捉えられるのは私一人しかいないのである。その重要性は人間関係云々では済まされないのだ。
ちなみに今回の北極遠征ではボディだけで10台のカメラを持ち込んだ。現地入りして、現場に合ったカメラを、その都度チョイスするためだ。それはすごい荷物となった。

大場さんは、その都度何十キロも流されてしまうが巻き返しは凄まじかった。すごいペースで北極点へ突き進む。いよいよ我々補給部隊&取材班の出番である。機材云々に関してはいつまでもぶつくさ言われたが、こちらも譲れない最低限度の機材であることを主張。意見は分断されたままの出発となった。

まず、北緯80度の気象観測所、ユーレイカまで飛ぶ。そこで、北極点の天候を見極め、瞬時に飛び立つ、というプロジェクトだ。問題はアイスフォグ。氷の滑走路に霧が立ち込めていたのでは着氷できないのだ。ここで驚いたのはまず、機内はパイプの椅子で、ほとんどを取り外し、ドラム缶を積み込むのだ。とにかく目いっぱい積めるだけ積み込む。機内にトイレはない。しかし水分を摂らなくては寒冷地ではよくない。このトイレと水分補給の関係は難しい。
気象観測所までは、わりとすんなり着いた。途中の島の山脈は絶景であった。見たこともない氷河の数々。無数のクレパス。ただただ平らな雪原。その白い世界が何処までも続く。フィルムがなくなるのではないかドキドキしながらシャッターを切った。装備には大量のフィルムが嵩張る。それも装備のうちなのだが、理解はしていただけなかったようだ。
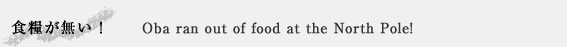
この時、大場さんは食糧が尽き果て遺書を書いていた。こちらでもそろそろ尽きるだろうとは予測していた。最悪、空中投下で補給する案も出され、準備に追われた。再び我々は飛び立つ。エルズメア諸島を抜けると、一面氷の世界だった。これが北極海か。リードは無数に広がり、プレッシャーリッジも波立っているのが上空からも判別できる。これは正直、どうなるのかと思った。尋常ではない世界なのだ。
ツインオッターはぐんぐん距離を稼ぐ。何時間機に揺られていたのだろう。機内がガソリン臭くなる。機内に積

んであるガソリンタンクから燃料タンクに空中給油しながらツインオッターは飛行するのである。こんなフライトは後にも先にも経験がない。プロペラ機は羽音がうるさい。でも、なぜか我慢できた。とにかく補給が最優先されるのだ。
今回はテリーさんも同道してもらった。長年北極で宿をやっているが北極点には行ったことがないのだという。大場さんは鼻に凍傷を負っているらしく、それを見極めてもらう意味もかねての同行だった。

ツインオッターのGPSが北極点を示した。遂に到着した。ここが北極点。しかし、なんの実感もわかない。窓からの世界は、ただただ真っ白な氷の世界だからだ。大場さんとのやり取りは、小型のシーバーで行われることになっていた。こちらから呼びかけるが、なんの応答もない。が、しばらくして返答があった。嗚呼、大場さんの声だ!小さなテントが北極海の氷の上に幕営されていたのが見えた。しかし、それは望遠レンズでも遠く小さい。

ツインオッターは超低空飛行を繰り返し、氷の滑走路を探す。ここで、酷い飛行機酔いになりそうなくらい機が揺れる。それはもう失速寸前まで減速して飛ぶのだ。それも超低空を。機長は一瞬で滑走路を見極め、あっという間に着氷してしまう。ツインオッターは大きなスキーを履いている。滑るように着氷し、プロペラを強烈に逆回転させ、短距離で止めてしまう。機長はいとも簡単に成し遂げてしまった。
しかし大場さんは元気そうだけど、テント内にいて、着氷したツインオッターを見失ったらしい。こちらは燃料と寒気の関係であまり居られない。パイロットたちは直ちにエンジンを保温カバーでくるみ始める。エンジンが冷え切ってしまったら2度と飛び立つことは不可能なのだ。
シーバーで何度か連絡するが、大場さんは空腹で動けず、しかも着氷した場所を見失った。降りてみるとわかるのだが、一面の雪景色で、ボコボコとプレッシャーリッジが乱立し視界は効かない。しかも天候は曇り空。ここで機長と判断が分かれた。機長は、少し時間がかかっても、ここまで来たほうがいいと言う。大場さんは、食糧を空中投下してくれと言う。
結局、空中から投下させる判断となった。こちらから歩いて行くには危険すぎる。初めて北極点に降り立ったが、プレッシャーリッジは想像以上の高さ、リードも雪を被っており、スキーを履いていない我々は余計北極海に落ちやすい。
エンジンカバーは外され、再びエンジンがかかる。急発進するが、いきなりツインオッターは停止した。下ろすはずの荷物があるし、滑走路が短いので飛び立てない。全員後部へ移動するよう指示が下された。機はめいっぱい滑走路の最後部へ下がり、聞いたことのないようなプロペラ音とともに離氷した。一瞬の出来事だった。このパイロットが並みの腕でないことは後日判明することとなる。
飛び立ったツインオッターは再び低空飛行で大場さんの居たあたりを旋回する。セスナよりははるか大きく、回転半径は大きい。機を傾け、ドアをバコッと開き、段ボールを、どんどん投下させてゆく。落ちた荷物がどうなっているのかはまったく見えない。霧が出てきたので低空飛行は無理だった。それでも1か所に集中させ投下させることの難しさを知った。機は旋回しながらでないと飛行できないからだ。しかもホワイトアウトすると墜落の危険性もある。

緊張の瞬間とは、私の人生、後にも先にもこれっきりだ。しかもすべての人、すべての事柄が命がけ。それでも、どこか冷静に事態を見ていられたのはなぜだろう。焦るようなことはなにもなかった。全員がなすべきことをしていた。注意すべきことは、投下する荷物が尾翼にぶつからないようにすることだ。北極点の猛烈な寒気が機内に入り込むが、誰も寒くはなかったと思う。誰もが熱い瞬間だった。
残念ながら、今回のフライトはこれで終了。帰りの燃料を考えるとそうなるのだ。それからの大場さんは、この補給でなんとか息を吹き返した。その時はわからなかったのだが、食糧が尽き果て、遺書まで書いていたのだから。
後日談だが、この時シュラフにくるみ投下した無線機も壊れてしまったようだ。食糧はばらばらに散らばり、それでも大場さんは食糧や手紙を拾い集め、生き延びることができた。良かった。本当によかった。
それでも、スタッフ一同、すっきりとはしなかった。声は聞けたが会話にはならなかったし、顔を見ることさえできなかったからだ。
もう一回、もう一回、飛ばなくてはきちんとした補給もできないばかりか、写真も撮れないこととなった。果たして、もう一回はあるのだろうか。帰りはなんとなく暗い雰囲気になった。ワンフライト300万円。これも大きくのしかかっていた。帰りは一気にレゾリュートまで帰搭する。
一度、この命がけの北極点補給フライトを経験すると、多少のことでは動じたり緊張したりしなくなる。自分が特に何をしたわけではないし、役立たずのかなり迷惑な存在だったのだろうが、そうは言っても、何事も経験なのである。

本来は、我々はこの補給フライトですべてのミッションが終了する予定であった。しかし、現実的に、ここで帰ってしまうと、誰も今後の補給に行ってあげられなくなる。私は写真が撮れないだけで済むが大場さんの命はどうなるのだろう。メインスタッフは、今後雪解けの北極の春までレゾリュートに滞在することとなる。メインスタッフと書いたが、それは私ではなくただの1名なのだ。大場さんの冒険の成功の鍵は彼に託されていった。だが、この今回の補給が完璧に行われなかったために、益々険悪な雰囲気は続くこととなる。

レゾリュートに帰った後、本国に連絡した。補給が完璧に行われなかったこと、写真が撮れなかったこと、私はただ、淡々と伝えるしかなかった。編集はかなりがっかりしていたが、それは全員同じ気持ちだった。私はただ、もう少し北極に残りたいことを告げた。私に残された時間が少ないことは火を見るより明らかだった。
春の嵐もブリザードだが、だんだん温かくなっていくのがわかる。マイナス10度を超えることもしばしばだ。

そんなある日、本国から国際電話が。高宇君、そろそろ日本に帰ってこない?取材費も100万円超えちゃったしさあ。私は電話越しに頭を下げ、こう言った。すみません!ここからは自腹でいいのでやらせてください!貯金もわずかだけど、少しあるので、それを当てます、と。